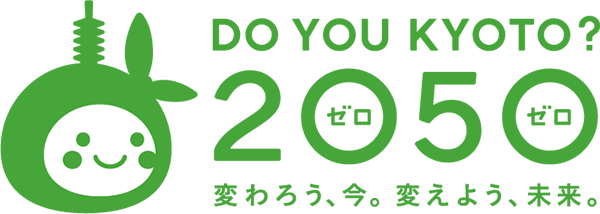JUNKANS
循環ズ
2025.07.09
食とわ × 循環フェス 〜企業訪問レポート〜
コンポストって意外と身近!環も、輪も、話も広げる「食とわ」の取り組み。
今回は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社様に、共創プロジェクト「食とわ」についてお話を伺いました。私たちの生活に当たり前にある「食」の循環について、貴重なお話をお聞きすることができました。

■目次
- お話を伺った方
- 学生インタビュアー紹介
- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
- 「食とわ」について
- 食とわのコンポストチャレンジって?
- コンポストが変える日々の生活
- レシピからはみだしてみよう
- サブインタビュアー新 美月(しんみづき)より
- 最後に
1. お話を伺った方

髙橋 諒 様
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
経営企画室サステナビリティ推進部 サステナビリティ戦略推進担当
プロフィール:
阪急阪神百貨店やイズミヤなどの小売を運営するH2Oリテイリングのサステナビリティ活動を推進。「循環ってなんやねん」と日々問いながら、小売ならではの顔が見える食の循環づくりを目指して奮闘中。仕事ではじめたコンポストの面白さを知り、習慣に。趣味はカメラ、好きな食べ物はえのき。
2. 学生インタビュアー紹介

入江 優歌(いりえ ゆうか)
龍谷大学経済学部現代経済学科の大学4年生。
商業高校時代に国内外の問題に対してビジネスアイデアを考える中で、自分自身も何かアクションを起こしたいと感じていました。
お下がりが身近にある環境や古着好きということからファッションロスに強く関心を抱いており、偶然出会った【¥0Market】に惹かれて循環フェス実行委員として活動しております。
大学では計量経済学を扱うゼミに所属しており、Rを用いて社会問題を分析しています。
今回は初めてメインインタビュアーとして記事を作成させていただきました。

新 美月(しん みづき)
2001年宝塚市生まれ、23歳。デザイナーだった母の影響で、幼少期からファッションに親しみ、大学ではサーキュラーファッションを専攻し、現在は残反活用と着物のアップサイクルを軸に、資源だけではなく人や価値が循環する仕組みを模索しています。大量生産・大量廃棄の現状に疑問を抱き1年間の休学中に国内のアパレル生産工場を巡っていました。復学後、繊維の街・福井県勝山市に拠点を移し、現在は京都にも関わりながら、現場の知恵を学び、地域資源を活かした循環型のものづくりに取り組んでいます。今年3月に大学を卒業し4月からは循環フェスの運営企画として、学生企画のサポートを行っています。
3.エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社について
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は「楽しい」「うれしい」「おいしい」の価値創造を通じ、お客様の心を豊かにする暮らしの元気パートナーというグループビジョンを掲げ、関西エリアを中心に、阪急阪神百貨店やイズミヤ、阪急オアシス、関西スーパーといった食品スーパーのほか、商業施設やコンビニエンスストアなどを展開されています。
4.「食とわ」について

「食とわ」は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社、株式会社地球Labo、一般社団法人フードサルベージの3社の共創プロジェクトです。
これまで個別に行われてきた「家庭用コンポスト実践」や「サルベージ・パーティ®」といった食品ロス削減の取り組みを土台に、生活者・企業・地域が一体となって新たな価値を創り出し、食品ロス削減と食べ物との新しい向き合い方を目指して立ち上げられました。
5.食とわのコンポストチャレンジって?
キッチンの生ごみを「捨てる」から「育てる」に変える3週間のコンポスト体験型プロジェクトです。微生物の力で生ごみを堆肥化し、その成果をみんなで共有しながら取り組みます。できた堆肥はみんなで持ち寄って街のみどりをいっぱいにしています。
期間中はLINEを用いて報告することとなっており、不安や疑問も気軽に相談できるのがうれしいポイントです。

「はじめの3週間、みんなでやろう」
コンポストを始めるってなかなかハードルが高いこと。
そんな勇気を出して始めたのに挫折してしまったら、せっかくの気持ちがもったいない。だからこそ、毎日LINEでのサポートが用意されており、仲間とつながりながら無理なく続けられる仕組みになっています。
食とわの「わ」には、循環を意味する「環」だけでなく、「輪」や「話」といった意味も込められているそうです。毎日誰かに報告し、見守ってもらいながら続けるコンポスト。
都市のなかでも、人とのつながりを感じながら挑戦できる取り組みとなっています。
ずっと冷蔵庫にあるけれど罪悪感があってなかなか捨てられなかったものをコンポストに入れると冷蔵庫の中がきれいになっていって、心も整理された気になります。
またその経験から「賞味期限が近づいているけれど、どうしよう」という意識が強くなることで、新しい料理法や保存方法を知るきっかけにもなります。
コンポストは堆肥を作るためのものですが、そこから得られるものは堆肥だけではありません。その過程で、一緒に取り組む方々とのつながりが生まれたり、ごみが減ることの楽しさを実感したりすることもできるのです。
6. コンポストチャレンジが変える日々の生活
髙橋さんは、私たちが毎日「食」と関わっていること、昔はその営みと自然がもっと近くにあったこと、そして今はそのつながりを感じにくくなっていることについて、こんなふうに話してくれました。
「私たちは生活者として『食』に関わらない日はありません。
かつては、食の営みと自然の営みがもっと身近につながっていました。
たとえば、家庭から出る生ごみは畑の隅に埋めることで土に還され、その土でまた作物が育つという循環が、日常の中にありました。
ところが現在は、都市化や生活様式の変化により、生産者と消費者の距離が広がり、自然と関わる実感が持ちにくくなっています。」
でも、コンポストチャレンジに挑戦することで、無意識に捨てていた生ごみに意識が向くようになります。
「大根の皮ってもっと薄くむけるかも?」「次は野菜の皮をきんぴらにしてみようかな」
そんな気持ちが、自分の中から自然と湧き出てくるのかもしれません。

with LOCAL ≠ for LOCAL
お店としてイベント等を開催すると、どうしても「おもてなしをする側」と「お客様」という関係が生まれがちです。
でも、この取り組みは、参加者自身が価値を生み出す場。
誰かに用意してもらうのではなく、参加者自身が能動的にアイデアを出すことで、活動の面白さや意義が深まります。こうした姿勢は、地域のために何かを「してあげる」のではなく、地域と共に立場を超えて、一緒にアクションを起こす関係性へとつながっていきます。
髙橋さんは「生活者の方と日々接しているという小売業の強み。私たちだからこそできることがあるのではないか。」と考えていました。
何度か繰り返すうちに、それは少しずつ人々の生活に馴染み、やがて当たり前の習慣になっていきます。そうして根づいた習慣が、さらに広がり、人々の意識や行動を変え、やがて文化として定着するかもしれません。このコンポストチャレンジはその大切な一歩を担っているのだと感じました。
7. レシピからはみ出してみよう
コンポストチャレンジと並ぶもう一つの柱が、「食とわクッキング」です。
家庭やお店で持て余す食材を持ち寄って、みんなで即興で調理する「サルベージ・パーティ®」にコンポストを掛け合わせたクッキングイベントです。

私たちは、スーパーにいつでもきれいな食品が並んでいることを当たり前のように感じていますが、その裏側で何が起きているのかを考える機会は少ないかもしれません。
「食とわクッキング」は、そんな見えにくい部分に目を向けるきっかけにもなります。
また、限られた食材を使って即興のレシピを考えるという経験も貴重です。
今はインターネットで検索すれば、細かくて丁寧なレシピがすぐに見つかります。
しかし、その丁寧さゆえに「この食材がないと作れない!」と感じてしまうこともあるかもしれません。
例えば、レシピには「じゃがいも3つ」と書いてあるのに、家には2つしかない。
「買い足さないと」と思ってスーパーに行った結果、結局余らせてしまう……。
そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。
でも、「食とわクッキング」でみんなで工夫しながら料理をすることで丁寧なレシピからはみ出してみるという柔軟な発想ができるようになります。
完璧でなくてもいい。曖昧でもいい。
情報があふれる今だからこそ、生活者として“ゆるさ”を持つことが、かえって豊かさにつながるのかもしれません。
8. サブインタビュアー新 美月(しん みづき)より
インタビュー前まで私が勝手に抱いていたコンポストに対する偏見。それは食ロスを無くすために、環境を守るために、意識をすこし高く持ってすること。でも髙橋さんとのお話を経て、その見方は180度変わりました。
おうちでお料理すると、あの億劫な生ゴミの処理はつきもの。よっぽど意識しないと生ゴミが一切でないお料理は難しいように感じます。また自炊をする一人暮らしの方は食材を使い切られず、ごめんなさいしながら食材を捨てた経験もあるはず。そんなちょっとした食材に対する心の重さを軽くしてくれるのがコンポストでした。コンポストがあれば、ちょっとした罪悪感を感じていた生ゴミや食べ残しが肥料となり、また次の命を育てる栄養になります。
食とわプロジェクトは、コンポストを通じた食材の循環だけではありません。コンポストで育った食材は「サルベージ・パーティ®」を通して、人と人をつなげる種となり、地域の循環を広げます。環境のためではなく、環境と共に。地域のためではなく、地域と共に。食の先にいる“誰か”を想いながら、日々の循環を育てていくH2Oリテイリングさん。「自分のために、できることから」。食とわプロジェクトは、そんな前向きな気持ちを後押ししてくれるように思います。
9. 最後に
今回は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社様にて「食とわ」の取り組みについてお話を伺いました。
「循環って難しそう」「環境問題って大変そう」 と感じてしまうかもしれませんが、実はそんな風に身構えなくて大丈夫なのだと感じました。ちょっとした工夫で暮らしが快適になれば、それも立派な循環です。
自身の中のハードルを下げて、ゆるくみんなで取り組んでいきませんか?
*エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
HP:https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/index.html
*食とわ
HP:https://shokutowa.jp/
Instagram:https://www.instagram.com/shokutowa/
食とわラジオ:https://open.spotify.com/show/6WY3f1CGRnxGtE6N4hjxz0